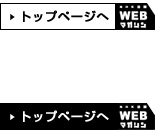私はほとんど英語が話せない、イタリア語は片言。夫は英語が話せるが、職業上の専門は筋肉とか体の部位とか。子どもはインターナショナルスクールに通っていたので発音だけはいい。そんなはんぱな三人が、カプリの港でいきなりカプリ賞事務局のアンジェリーニ夫妻に迎えられてなんとかホテルにたどりついたりいっしょにごはんを食べたりしたのだから、どれだけ珍道中かわかろうというものだ。
もちろんあとからイタリアの友人たちが来たし、通訳もついたし、エージェントも来た。だから授賞式近辺はなんとかなった。 でも、この旅では日程の関係でなぜか家族三人だけという状態が全部で三日間くらいあった。そのときはなんてたいへんなんだろう、とめまいがしたが、今になってみるといちばん珍しいよい思い出になった。
事務局のアンジェリーニさんはNY在住で、そのせいだろう、イタリアの賞を受けるときの「しきりがでたらめだからもうなんでもいいや」みたいな感じはなかった。きちんとオーガナイズされていたし、彼らがアートを愛していることがしみじみと伝わってきた。奥さんであろうオルガさんは若いときそうとうに美人だっただろうと思われるとても上品な人で、いつでもささやくように美しいことを話した。私たちが困っていたり、子どもが寝てしまったり、ほんとうはもう帰りたいようなときになるとそっとやってきて助けてくれた。
文学を、アートを愛するそんな人たちがしっかりした土台となっているからこそ、このような小さく魅力的な賞が存続しているのだろう。賞金を一円でも高くするよりも、ホテルやホテルの食事を負担してくれて、カプリを味わってもらおうという試みもとても上品だと思った。
スポンサーのひとりであろう大富豪の実業家ドロテアさんは八十くらいのイタリアと日本のハーフのご夫人で、いつも迫力のある毅然とした姿で、私たち家族にヨーロッパの上流階級の生活をかいまみさせてくれた。大実業家であるおとうさまのあとをついで女一人やってきたその人生は少し聞いただけでも想像を絶するもので、彼女がそこにいるだけで大河ドラマを見ているような気分になった。
もしも私が「上流階級志望」だったら、パーティにやってきたそのきらめくような人々…世界を回してきた実業の大物たち…と少しでも近づこうとして、服をそろえたり英語を勉強したり、きっとたいへんだっただろう。でも、全然興味がないから、じっくりと観察することができた。お金持ちの大変さ、甘美さ、複雑な人生を。