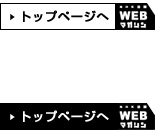それでも、冒頭に書いたように、いちばん思い出深いのは家族で何回も同じカプリの町を歩いたことだ。
ホテルのとなりには有名なジェラートの店があり、コーンを店先でいちまいいちまいおせんべいのように手やきしている。夫とチビと毎日のように行列に並び、どのアイスを食べようか、と相談しあった。お金持ちのリゾートであるカプリの町の物価はものすごく高い。ちょっとしたショッピングをするのも数万単位だ。だから特になにを買うでもなく、ウィンドウを眺めながらぶらぶら歩いた。広場にはすぐ出てしまうし、港に出ても船に乗らない限りそんなに大きな用事はないし、ホテルの周りをうろつくのがいちばんだった。
なんとか交渉して値切って小舟に乗り、島を一周して船酔いしながら帰ってきたこと、それでも切り立った崖と海の美しい景色が圧倒的だったこと。
炎天下を歩いていたらチビが鼻血を出して高級レストランのマダムに親切にデッキで寝かせてもらったこと。そのとき泣きながら寝ている八歳のチビが赤ちゃんのときみたいに見えたこと。
ホテルの細長い部屋からいつも三人で夕日を眺めたこと、カプリの町の真ん中にあるその高級ホテルのレセプションやレストランのおじさんたちと、いつしか冗談まじりの気さくなやりとりをできるほどに仲良くなったこと。
賞をいただくって確かにすてきなことだと思う。認められたのかもしれないし、自分の小説がイタリア国内で浸透していることをしみじみと確かめることができる。でも、なによりもいちばんすてきなのはそういう小さな個人的な思い出だ。それは、自分でカプリに行こうと決めてチケットを買ってホテルを決めたときには決して味わうことができないなにかなのだ。
ママが社会的なことに関わって仕事をしている姿、それを祝って手伝ってくれるパパの姿、そして仕事を終えてリラックスして家族に戻ったときのだらしないひとりの人間としての両親の姿…みんな子どもに見せることができる。すばらしい景色やいろいろな国のいろいろな人の姿といっしょに、子どもの心には思い出が残る。
それをもらえたことがいちばん嬉しかったなあ、と思うのだ。